痛みの治療といえば電気刺激やストレッチが定番ですが、最近またじわじわと注目されているのが「温熱療法」です。とくに、「深部まで届く」ことをウリにしている機器がいくつかあって、その中でも一部のクリニックやスポーツ現場で人気なのが、テクノシックスRCという高周波治療器。
名前からしてちょっと近未来っぽいですが、要はラジオ波(高周波)を使って、体の内側からじわじわと温める機械です。ラジオ波は、電波の一種で、特に周波数が高いものを指します。分子を振動させて体の深い部分を温めることができ、血流を良くしたり、筋肉のコリをほぐすのに役立ちます
ただ、似たような目的で使われる機器に超音波治療器もあります。両者とも「温めてほぐす」系の治療機器ですが、仕組みも使い方もまったく違う。というわけで今回は、「どっちがどう違うのか?」を、科学的な視点からまとめてみました。
テクノシックスRCの正体とは?
まずはざっくり概要から。
- 使用エネルギー:電磁波(ラジオ波)
- 加熱の仕組み:誘電加熱(分子を揺らして摩擦熱を生む)
- モード切替:CAP(筋肉や皮膚)/RES(腱や骨など)
- 作用深度:深部まで届く(調整可能)
- 禁忌:金属インプラント・ペースメーカーなどは絶対NG
この機械の面白いところは、「どの組織にどれだけ熱を届けるかをモードで選べる」という点。水分の多い組織(筋肉、血管)にはCAPモード、骨や腱などの固くて乾いた組織にはRESモード、といった使い分けが可能です。
温熱の効果としては、古典的な研究でも以下がよく知られています。
- 血流改善(筋疲労や回復を助ける)
- 筋緊張の緩和(スパズム軽減)
- 組織の伸展性向上(可動域アップ)
- 疼痛軽減(ゲートコントロール理論+代謝物の除去)
このあたりは、従来の超音波療法と重なるところも多いですね。
超音波との違いを比較してみる
では、ここから本題。テクノシックスRCと超音波治療器の違いは何か?
主なポイントを表にまとめると以下のようになります。
| 比較項目 | テクノシックスRC(高周波) | 超音波療法 |
|---|---|---|
| エネルギー | 電磁波(ラジオ波) | 音響波(超音波) |
| 熱の発生原理 | 誘電加熱(分子摩擦) | 音響吸収(振動・摩擦) |
| 作用深度 | モード切替で調整(CAP/RES) | 周波数で調整(1MHz深/3MHz浅) |
| 非温熱効果 | 明確なメカニズム不明 | パルスモードで確認されている |
| 金属インプラント | 絶対禁忌 | 一般的には使用可能 |
| 主な適応 | 慢性疼痛、筋緊張、可動域制限など | 急性期~慢性期まで幅広く対応可 |
| 導入コスト | 高め(高機能) | 中~高(機種により幅大) |
特に重要な違いが、金属インプラントの有無と非温熱効果の有無です。
金属インプラント:高周波はNG
テクノシックスRCは金属がある部位には絶対に使ってはいけないというルールがあります。高周波電流は金属に集中してしまい、やけどリスクが跳ね上がるためです。
一方、超音波はその点で比較的安全。もちろん全くリスクがないわけではありませんが、インプラントがあっても使える場面が多いです。
非温熱効果:超音波に軍配
パルスモードの超音波には、「細胞膜の透過性を上げる」「炎症メディエーターを散らす」などの非温熱的な効果があることが確認されていて、急性期の腫れや痛みには特に有効です。
一方、テクノシックスRCでも「非温熱」モードがあるとは書かれているものの、それが具体的にどう効くのかは、エビデンスとしてはまだ不透明な段階です。
実際の使い分けはどうする?
ここまでの違いをふまえると、両者には得意分野があることがわかってきます。
超音波が向いているケース
- 金属インプラントがある
- 急性の炎症(腫れや痛み)
- 骨折治癒を促進したい(LIPUS)
テクノシックスRCが向いているケース
- 深部の筋肉や関節をしっかり加温したい
- 高度な柔軟性改善を狙いたい(特に慢性拘縮)
- スポーツ現場でのパフォーマンス向上や回復促進
たとえば、腰部の筋硬結や股関節の拘縮が強い患者で、金属が入っていない場合は、テクノシックスRCのRESモードが強力に働く可能性があります。私自身も試してみましたが、使用後にかなり可動域が改善する例も見られました。
まとめ:エビデンスと臨床のバランスを取る
テクノシックスRCは、確かに魅力的な機能を備えた治療器です。深部まで届く温熱感は、患者さんの主観的な満足度も高いですし、術者としても「しっかり届いてる感」があります。
とはいえ、現時点でのエビデンスはまだ限定的。とくに、超音波との直接比較試験や長期的なアウトカムを評価したRCTはほぼ見当たりません。
逆にいえば、臨床判断がますます重要になる領域でもあります。機械の特性とリスクを理解したうえで、「この患者さんにはどちらが合うか?」を丁寧に見極めること。
今後、独立した研究や比較試験が増えていくことを期待しつつ、現場では柔軟に使い分けていきたいところです。

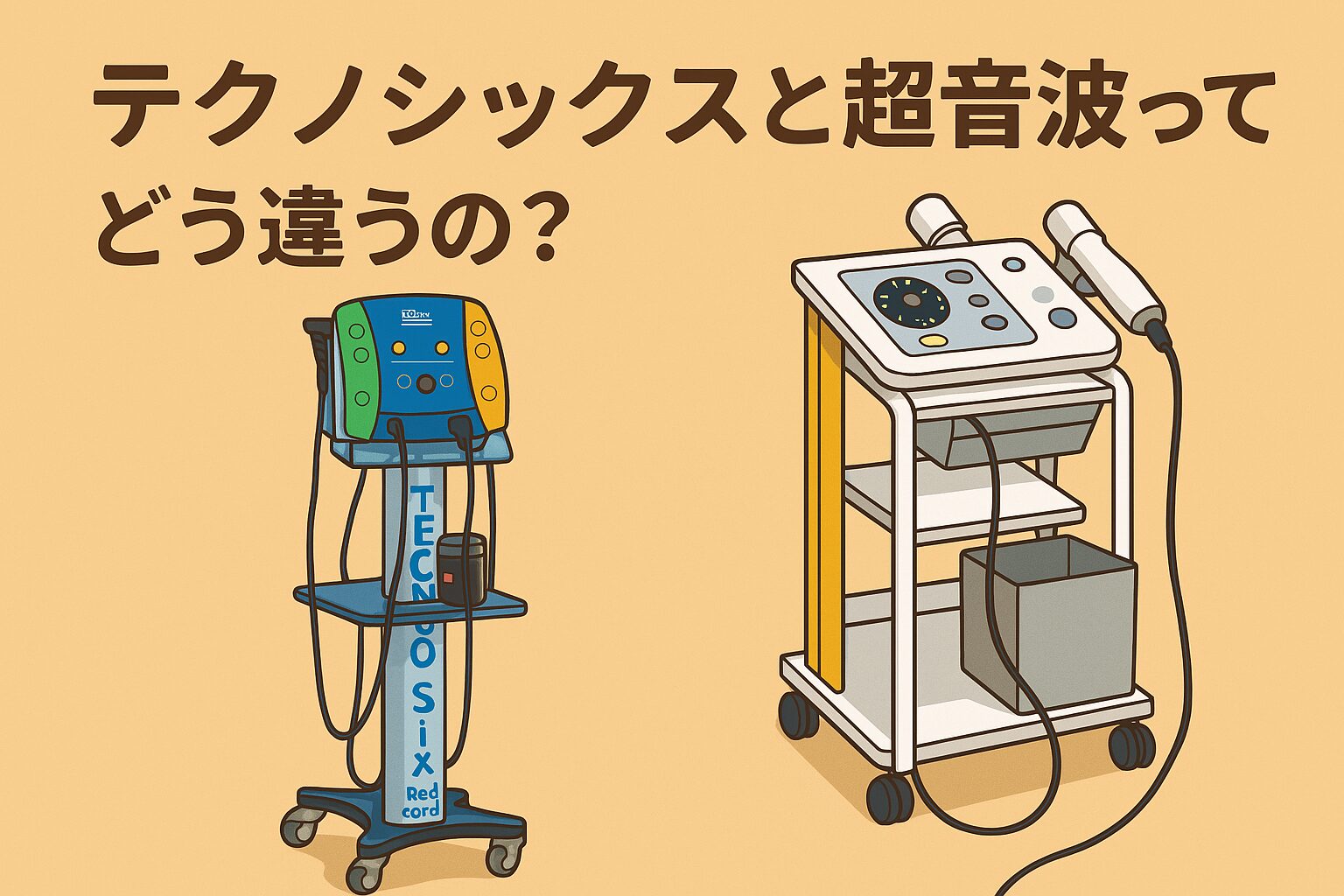


コメント