
石破政権が来月から導入する、ガソリン1リットルあたり10円の補助再開と、電気・ガス料金への再支援。これらは一見して国民を物価高から守る善意の政策に見えるかもしれない。しかし自由市場の原則と歴史的知見に照らせば、こうした介入は長期的な進歩と持続可能性を損なう可能性がある。
歴史が語る「価格操作」の代償──そして市場を活かした国々の教訓
1970年代の石油ショック時、多くの政府は価格を抑制しようと補助金や統制に走った。その結果、ガソリンスタンドの長蛇の列、燃料の慢性的な不足、インフレと財政赤字に見舞われた国も多かった。一方で、市場価格を尊重した国々では、価格という「痛み」を契機に構造改革と技術革新が進んだ。
たとえば西ドイツでは、価格を歪めることなくエネルギー効率化を国家戦略とし、1980年代には産業部門のエネルギー使用効率が25%以上向上した。これは後に再生可能エネルギーへの移行を支える土台にもなった。
スウェーデンでは、価格上昇が重油からの脱却を促し、森林資源を活用したバイオマスや原子力への転換が進んだ。1970年代に40%を占めていた石油依存度は、2020年代には20%以下にまで低下し、世界でも脱炭素化が進んだ国の一つとされている。
アメリカでは連邦政府が一時的に補助金政策を採ったものの、カリフォルニア州のように独自の高い燃費基準を設けた地域では、高価格に応じたイノベーションが促された。その延長線上でトヨタ「プリウス」やテスラなどが台頭し、世界の自動車産業を変革する土壌が生まれた。
つまり、価格というシグナルを尊重した国々では、人間の創意工夫が発揮され、新たなエネルギー経済が形成される下地が生まれたのである。
補助金は公平性も効率性も問われる
今回の補助政策には二重の問題がある。第一に、逆進的で不公平になりがちである。富裕層の大型車ユーザーも、生活に苦しむ庶民も、同じように補助を受ける。これでは社会的弱者への再分配とは言いがたい。
第二に、財政規律と制度的透明性が欠けている。補正予算を回避し、予備費や既存基金を使うことで、政策の妥当性を議会で検証する機会が失われる。それは財政民主主義への逆行であり、将来世代への負担の先送りにもつながりかねない。
加えて、価格を歪めることでエネルギー消費が抑制されず、再生可能エネルギーや省エネ技術への投資インセンティブも相対的に弱まる可能性がある。これは、短期的には安心を与えるかもしれないが、長期的には脱炭素や技術革新の機会を損なう懸念がある。
解決策は自由にある──市場に委ねよ、創意に任せよ
我々が信じるべきは、国家による価格操作ではない。価格は問題の一部ではなく、解決の手段である。高いガソリン価格は消費を抑え、公共交通や電気自動車への移行を促す。高い電力料金は、省エネ製品や再生可能エネルギーへの投資を正当化する。
価格こそが、我々が「より少なく、より賢く」使うことを学ぶ最大の教師なのだ。補助金という麻酔ではなく、市場という薬を。我々が必要としているのは「保護」ではなく「解放」である。
自由市場の中でこそ、人間の創意工夫は最も大きな成果を発揮する。国家が価格を抑え込むのではなく、価格が問題を解決する道を示してくれる。それは過去が教える一つの教訓であり、未来にも必要とされる知恵である。

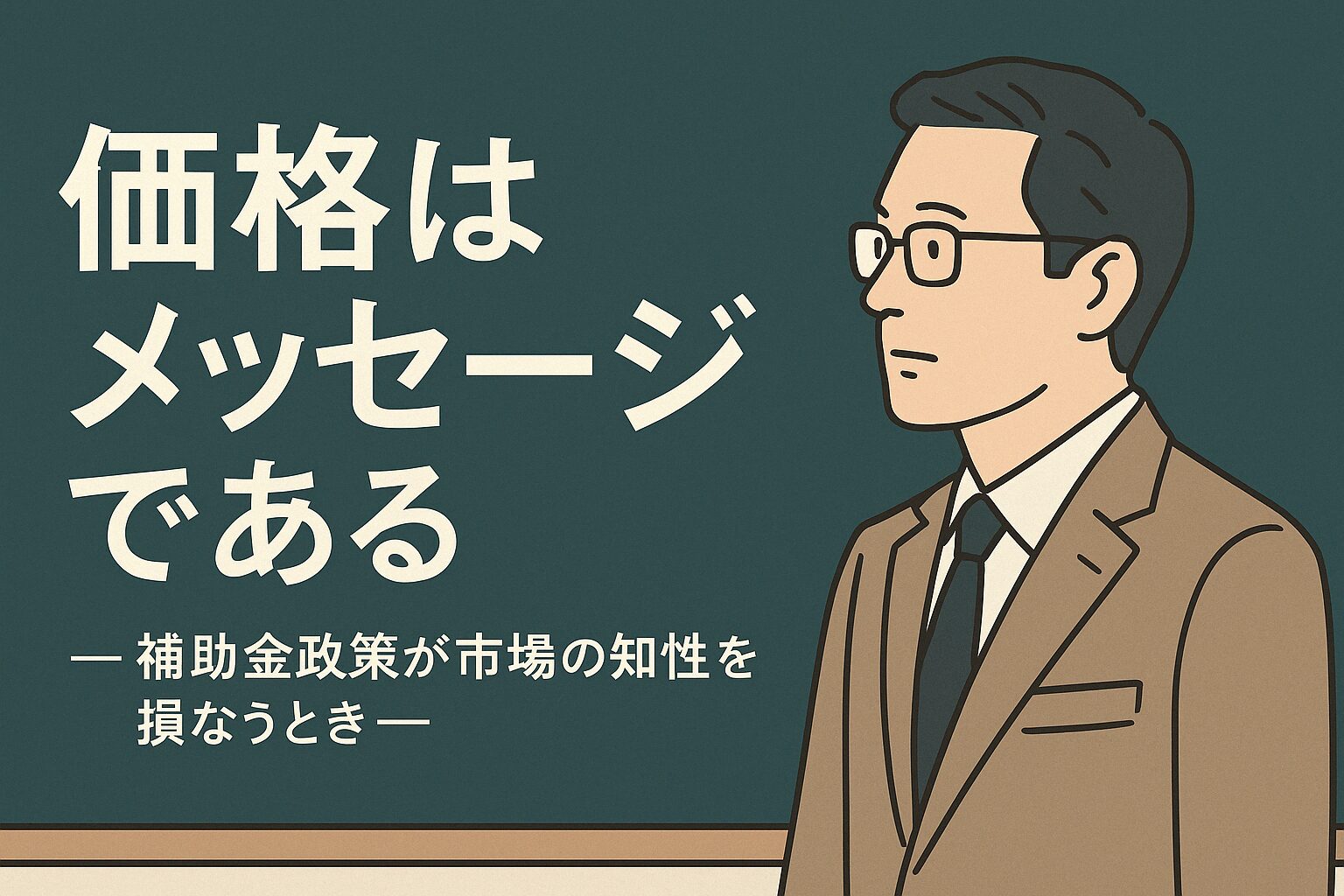
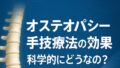

コメント