最近、整体やカイロプラクティックに加えて、「オステオパシー」という言葉を耳にすることが増えてきました。なんでも、アメリカでは正式な医学教育を受けた「DO(Doctor of Osteopathy)」がOMT(Osteopathic Manipulative Treatment)という手技を駆使して、痛みや機能障害にアプローチしているとのこと。
「ポキッ」という音とともに背骨を鳴らされた経験のある方なら、あの一瞬の快感を覚えている人も多いはず。でも、それって本当に効いてるの? というわけで、今回はOMTに関するエビデンスの網羅的レビューをもとに、どの手技がどの症状に効くのかを本気で調べてみました。
「全人的アプローチ」は科学にどう向き合うのか?
OMTの根底には「構造と機能は不可分」「身体には自己治癒力がある」といった、いわばホリスティック医療的な哲学が流れています。これは「体・心・魂の統合性を大事にする」という思想で、個人的にはとても共感できる考え方です。
がしかし、問題はそこではなく、「それ、エビデンスあるの?」という点です。特に現代の医療では、ランダム化比較試験(RCT)が治療効果のゴールドスタンダード。全人的で個別化されたアプローチは、どうしてもこの枠組みに収まりきらない。結果として、「OMTはよくわからない」「エビデンスが限定的」と言われてしまうのです。
とはいえ、それでも研究は進んでいます。以下では、主要なOMT手技の効果とエビデンスレベルを症状別に整理してみましょう。
SMT/HVLA(スラスト手技)
いわゆる「ポキッ」と鳴るアレ。関節の終末域に高速・低振幅の力を加えることで、可動域改善や痛み軽減を目指します。
MFR(筋膜リリース)
こちらは「ふわっ」と優しく筋膜を伸ばすアプローチ。
- 慢性腰痛の疼痛軽減に関しては、「中程度の質のエビデンス」で有効性が示されています
- ただし、機能改善については「非常に低い」質のエビデンスにとどまっており、「痛みは楽になるけど動けるようになるわけじゃない」かもしれません。
MET(マッスルエナジーテクニック)
患者の自力筋収縮を利用して関節可動域を広げる手技。PNFに似ていますが、よりマイルド。
臨床での使い勝手もよく、比較的安全性が高いのもポイントです。ちなみに僕も、ストレッチの補助としてMETっぽい手技を取り入れることがあります。
CST(頭蓋仙骨療法)
一方で、最もエビデンスに乏しいとされているのがCST。
- 「一次呼吸メカニズム」や「頭蓋リズムインパルス」といった理論は、生物学的妥当性に疑義あり
- ほぼすべての疾患に対して有効性を示す高質なエビデンスは存在しない
それでも広く使われ続けているのは、「触れてもらう安心感」「施術者との関係性」といった非特異的効果が大きいためでしょう。科学的には疑問ですが、プラセボを超える何かがあるのかもしれません(未検証ですが)。
研究デザインが追いつかないという問題
ここで強調しておきたいのが、OMTの効果が低いのではなく、研究デザインが難しいという点。
- 個別化が前提のOMTに、標準化プロトコルを求めるRCTは相性が悪い。
- 手技療法では、プラセボ対照群の設定が困難(「偽の手技」でも効果が出てしまう)。
- 「ポキッとすれば痛みが和らぐ」という効果の多くは、実は非特異的要因(注意、触れられる、共感など)によってもたらされている可能性。
このあたりは、科学と実践のギャップをどう埋めるかという、医療全体の課題でもあります。
結論:OMTは「効く」が、「いつ、何に、どのくらい」は慎重に見るべし
現時点での結論はこうです:
- 慢性腰痛に対しては、HVLA、MFR、METはいずれも「選択肢としてアリ」。ただし「劇的に効く」とは限らない。
- 頚部痛はMETが最有望。HVLAやMFRは併用で効果が出るかも。
- CSTやVM、リンパポンプなどは、今のところ「様子見」が妥当。信じるかどうかはあなた次第。
科学的な裏付けがすべてではありませんが、少なくとも「効くかどうかを知りたい」なら、やはりエビデンスが語ることに耳を傾けるべきです。
「エビデンスがすべてではないが、無視もできない」ーーこのスタンスが、科学と実践のちょうどいい接点なのかもしれません。OMTに限らず、あらゆる治療法を評価するときに、僕たちが忘れてはならない視点です。

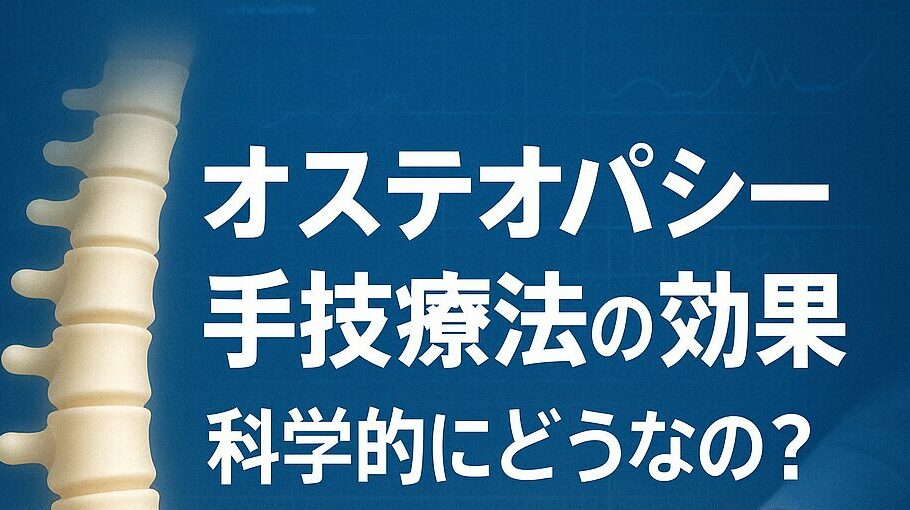


コメント