日米関税交渉でのコメ輸入割合に関する投稿がSNS上で注目を集めました。
今必要なのは、自民党政府が長きに渡って押し付け続けた減反政策により、弱り果ててしまった国内のコメ農家を直接所得補償によって守り、安定した生産を確保することであって、備蓄米を食い潰した挙句、アメリカの圧力に屈してコメ輸入を拡大するなど言語道断。有り得ない。
この投稿は、政府の農業政策に強く反対する内容です。しかし、ここで語られていることは本当に事実に合っているのでしょうか。実際の制度や数字をもとに、一つずつ確認してみます。
(形式的には)減反政策はもう終わっています
投稿では「長きに渡って押し付け続けた減反政策により、弱り果ててしまった」と書かれていますが、国がコメの作付け量を割り当てていた制度(減反)は2018年に終わっています。現在は農家や産地が自分たちで生産量を調整しています。
ただ、水田で飼料用米・麦・大豆などに転作すれば10a あたり最大 10.5 万円の補助が出る「水田活用直接支払交付金」(以下 水活)が残り、主食用米を減らすインセンティブは依然強いです。さらに農協・自治体は毎年「適正作付量」の目安を農家に示しており、これを事実上の減反政策とみることもできます。
とはいえ、農業が苦しくなった原因は、減反だけではありません。農家の高齢化や、コメの消費量の減少、農地の整備が進まないことなど、いくつもの問題が関係しています。
直接所得補償はすでに実施されています
「農家を守るには直接所得補償が必要だ」という主張もありました。
| 主な仕組み | 2025(令和7)年度 当初計上額 | 補足 |
|---|---|---|
| 水活(転作支援) | 2,870 億円(参議院) | 麦・大豆・飼料用米など |
| ゲタ・ナラシ等(経営所得安定対策) | 5,000〜6,000 億円 | 全農業補助の 2〜3 割を占める(財務省) |
ですが、日本ではすでに水田活用直接支払や経営所得安定対策といった形で、毎年2,000億円以上の補助金が支払われています。
「更なる直接所得補償が必要だ」という言い方なら納得できますが、直接所得補償がないような言い方は不正確だと思います。
備蓄米はまだ残っています
投稿では「備蓄米を食い潰した」と表現されています。
2025年春から夏にかけて、政府は物価高対策として備蓄米を大量に放出しました。たしかに備蓄の量は減りましたが、ゼロになったわけではありません。
政府の目標である100万トンに対し、2025年7月時点ではおよそ30万トンが残っています。
「食い潰した」という表現は、正確とは言えません。
安全水準を大きく割り込む懸念は事実ではあるので、どれぐらいが備蓄米の適正な量かを議論していく必要はあると思います。
輸入は増えていません(内訳が変わっただけ)
「アメリカの圧力に屈して輸入を拡大」という言い方も、誤解を招きます。
日本はWTOのルールに基づき、毎年77万トンのコメを外国から輸入することを義務づけられています(ミニマム・アクセス米)。
2025年7月の日米合意では、この77万トンのうちアメリカ産の割合を増やすという内容でしたが、輸入全体の量は変わっていません。
「輸入拡大」とは言えず、事実に基づかない表現です。
これとは別に、民間が関税を払ってでも外国のお米の輸入量を増やしている現象は起きているので、それが農家にとって危機だという考え方なら納得できますが。
なぜ誤った主張が広がるのか
SNSでは、強い言い切りやわかりやすい敵味方の構図が注目を集めやすく、複雑な事実が置き去りにされることがあります。
今回の投稿も、その影響で多くの人に共有されたと考えられます。
農業や食料の政策について考えるときは、次の3点が大切です。
- 制度の内容や変更時期を確認すること
今ある制度か、過去の制度かを正しく理解しましょう。 - 具体的な数字を確認すること
備蓄量や補助金の額など、事実をもとに話すことが大切です。 - 「ない」ではなく「足りない」かどうかを見分けること
制度がまったく存在しないのか、あっても十分でないのかで、取るべき対策が変わってきます。
コメの価格や農家の収入、備蓄や輸入の方針など、農業政策には多くの課題があります。
しかし、正しい議論をするには、まず事実を正確に理解することが出発点です。
感情や印象ではなく、制度や数字をもとに話すことが、問題を解決する第一歩になるはずです。
それではさようなら。

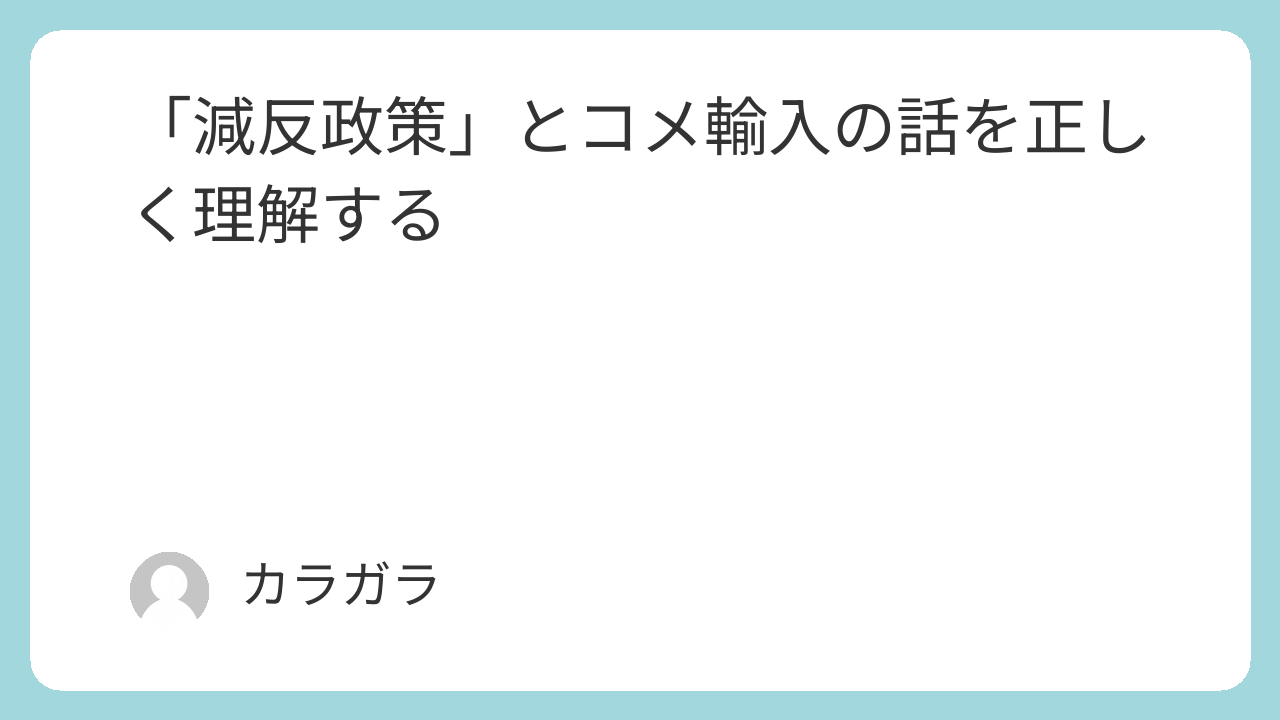
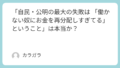

コメント